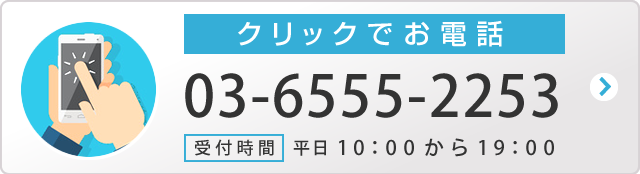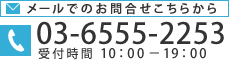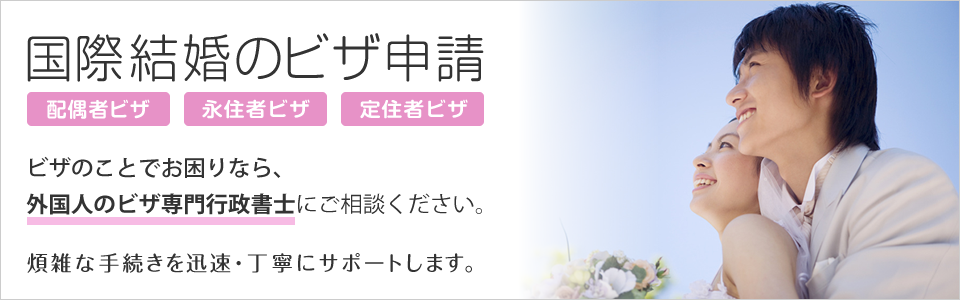国際結婚の年齢差が大きいと配偶者ビザが取りにくいのか?
これから国際結婚される方は、結婚相手と自分の年齢差について考えることもあると思います。
「お互いが良いなら年齢差は関係ない!」まさにそうですが、
せっかくなら年の差婚や夫婦の年齢差の割合について知ってみませんか?
本記事では、年の差婚の特徴、そして夫婦の年齢差や年齢差による離婚率を統計で見ていきます!
「年の差婚」とは
「年の差婚」に明確な定義はありませんが、大体10歳以上の年齢差を指す場合が多いと思います。
本記事でもこれくらいの年齢差を年の差婚と定義して、話を進めて参ります。
「年の差婚」の特徴
年の差婚による夫婦生活でよくあることを見ていきましょう。
良いことも良くないこともあげていきますので、参考にしていただければと思います!
①様々な刺激を得られる
年齢がどうであれ夫婦生活で得られる刺激はたくさんあると思います。
しかし、夫婦の年齢差が開いているというのであれば、より多くの刺激を得られるのではないでしょうか?
10歳以上も違うのなら、幼少期から学生時代、社会人になるまで、2人が見てきた社会環境には多くの違いがあると思います。そんなところから、価値観が一致すれば、毎日が新しい発見で溢れた夫婦生活になるのではないでしょうか?
②夫婦喧嘩にはなりにくいかも?
年齢差が大きいと、お互い考え方が違う点が多いと前々から割り切るかもしれません。
そうなれば、2人の考えが違う、相手の言っていることが理解できないといった理由でケンカになることも少なくなるのではないでしょうか。
③夫婦の歳が違うから頼りにできる
年齢が違うから相手を頼りにできるところがあると思います。
相手が年下であれば、体力を必要とする仕事を任せやすくなるかもしれません。
一方で相手が年上なら、いざという時でも今までの経験を活かして、問題を解決したりアドバイスをくれるかもしれません。
あくまでも例ですが、年の差婚で相手を頼りにできると実感する時が必ずあるでしょう。
④年齢差による違いが悪い方向になる可能性もある
夫婦の年齢差は、良い方にも悪い方にも向かいます。
年齢の違いが、互いに刺激を与えてくれるようなら問題ありませんが、必ずしもそうなるとは限りません。
違いが多いと理解しながらも、夫婦生活で自分がこだわってやりたいところは話し合っておくのが良いでしょう
年の差婚はどんな人におすすめ?
年の差婚であっても、夫婦円満に過ごせるのはどんな人でしょうか?
年の差婚に向いている人の特徴をいくつか挙げていきます。
①【男性】年の差婚に向いている人
職場などで、普段から若い人と接していて、若い世代への理解もあり、自分が歳をとっていても若さの感覚を持ち続けていられます。
また身だしなみや体型からも、若さを感じる。
こうなれば、年の差を感じさせない夫婦になれるでしょう。
②【女性】年の差婚に向いている人
自分とは歳が違う、そんなよく分からない世界にも飛び込んでいける人に向いています。
夫婦生活をしていく過程で初めて知ったことにも興味を持つ好奇心旺盛な性格であれば、互いに遠慮せず会話できるので、仲が良い夫婦になれますね。
【統計】夫婦の年齢差で多いのは?
では実際に、夫婦の年齢差で多いのは「何歳差」なのでしょうか?
厚生労働省の人口動態統計年報によると、下記のようになっています。
夫が7歳以上年上の夫婦の割合:10.6%
妻が4歳以上年上の夫婦の割合:6.4%
そして、年齢差が開くほど、その割合は少なくなっています。
ちなみに、夫が20歳以上の夫婦の割合は、0.1%以下でした。
1000組に1組の割合ということですね。
【統計】年齢差と離婚率はどんな関係がある?
夫婦の年齢差と離婚率には相関があるのでしょうか?
結論からいうと、夫婦の年齢差が開くほど、離婚率も上がります。
離婚弁護士ナビ編集部が行ったアンケートによると、離婚率は夫婦の年齢差が大きいほど高い傾向にあります。
出典:離婚弁護士ナビ
国際結婚夫婦の年齢差と配偶者ビザの関係
前述したように、今の日本では、90%以上の夫婦が年齢差7歳未満であり、年齢差が高いほど離婚率も高くなるという傾向にあります。
配偶者ビザの審査では、こうした統計データも少なからず考慮されます。
ただ、現場感覚としては、国際結婚の場合は年齢差15歳未満であれば、それほど厳しくは審査されません。書類に不備や不足がなく、完璧に申請すれば許可になっています。
年齢差が15歳を超えてくるあたりから、少しずつ審査が厳しく、慎重になります。配偶者ビザは、申請すれば簡単に取れるものではありません。自力で申請して、もし配偶者ビザが取れないと、相手からあらぬ誤解を持たれることもあります。
確実に配偶者ビザを取りたい方は、行政書士など、専門家のサポートを受けることをお勧めします。